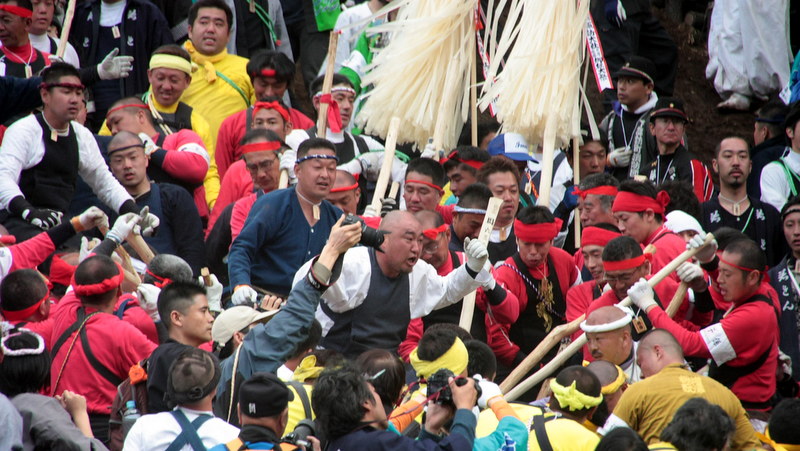御柱祭
命がけの木落しと人々の絆が燃える、諏訪の大祭
2026/04/01 - 2026/06/14
6年に一度、長野県諏訪地方の静かな山里が、御柱祭の熱気と歓声で一変します。千年以上にわたり続くこの大祭では、山中で伐り出された巨大なモミの木が、村人たちの手で急斜面を滑り降り、諏訪大社の四隅に建てられます。木の香り、土と汗の匂い、地鳴りのような掛け声と歓声、そして命をかけて丸太にまたがる男たちの姿——御柱祭は、見る者すべての心を揺さぶる“生きた伝統”です。
祭りは「山出し」と「里曳き」の2部構成で、4月から6月にかけて数週間にわたり開催。全国から50万人以上が訪れ、スリルと迫力、地域の誇りを体感しに集まります。日本屈指の勇壮な祭りを味わいたい方、写真好き、文化と人の熱気を感じたい方におすすめです。
主な見どころ
山出し(木落し)
祭り最大の見どころは「山出し」。長さ16メートル、重さ10トンを超えるモミの巨木を、何十人もの男たちが山道を曳き下ろします。クライマックスは「木落し」。勇者たちが丸太にまたがり、ほぼ垂直の急坂を一気に滑り降りる姿に、観客からは歓声と悲鳴が上がります。木のきしむ音、泥や松葉の匂い、地響きのような「よいさ!よいさ!」の掛け声が山にこだまします。
里曳き(御柱建て)
里曳きでは、山から運ばれた御柱が町を練り歩き、賑やかな音楽や旗、華やかな衣装の参加者たちとともに諏訪大社へ。神社では綱と人力だけで柱を立ち上げる「御柱建て」が行われ、四隅に御柱がそびえ立つ瞬間には大歓声が響き渡ります。鈴の音や旗のはためき、太鼓のリズムが祭りの高揚感を盛り上げます。
衣装と装飾
参加者は赤・青・白の法被や鉢巻、たすき、家紋入りの衣装で彩られ、足元は白足袋や藁草履。手にはタオルを巻き付けて滑り止めにします。御柱にはしめ縄や紙垂、色とりどりの幟が飾られ、沿道も旗や提灯で華やかに彩られます。
文化・歴史的背景
御柱祭は1200年以上の歴史を持ち、諏訪大社の御柱(神域を守る柱)を新しく建て替えるために行われます。木を伐り、運び、建てる一連の行為が神の力を呼び込み、地域の繁栄や安全を祈願する重要な神事です。諏訪の人々にとっては家族や地域の誇りであり、世代を超えて受け継がれる人生の節目でもあります。
国の重要無形民俗文化財にも指定され、地元だけでなく全国から注目される一大イベントです。
参加者の声
「東京から友人と山出しを見に来ました。泥が飛び、みんなで声を合わせて…五平餅を食べながら大興奮!こんなに熱い祭りは初めてです。
豆知識
- 御柱は1本10トン以上、長さ16メートルにもなります。
- 寅年・申年(6年に一度)に開催されます。
- 木落しは日本一危険な祭りのひとつといわれています。
開催日程
御柱祭は6年に一度、長野県諏訪市の諏訪大社で開催されます。
開催日程は変更になる場合があります。最新の情報は公式サイトなどをご確認ください。
開催が近いお祭り
クケリ祭り スルヴァ ブルガリア
ブルガリアの冬を追い払う、精霊と火と鐘の祝祭
2026/01/22ディナギャン フィリピン
イロイロが誇る信仰・伝統・ダンスの轟く祭典
2026/01/22オーロラ・フェスティバル ノルウェー
北極の夜に音楽とオーロラが舞うトロムソの奇跡
2026/01/25バスクのカーニバル スペイン
バスク山間に響く“太古の音と春を呼ぶ祭り”
2026/01/26アップ・ヘリー・アー イギリス
シェトランドに炎とヴァイキングの誇りが燃え上がる夜
2026/01/29ウインタールード カナダ
氷と光と笑顔があふれるカナダ首都圏の冬のワンダーランド
2026/01/30ヴィアレッジョのカーニバル イタリア
巨大な紙粘土の傑作が織りなす壮観なパレード
2026/01/30カンデラリア祭 ペルー
チチカカ湖畔に響く信仰とフォルクローレの大舞踏祭
2026/01/31タイプーサム マレーシア
バトゥ洞窟を彩る、祈りと苦行の壮絶な巡礼祭
2026/01/31ジャイサルメール砂漠祭り インド
ラジャスタンの黄金の砂丘が色と文化で輝く日